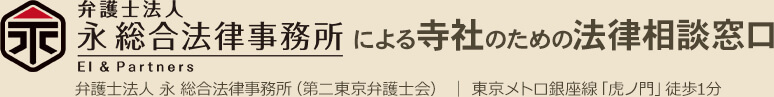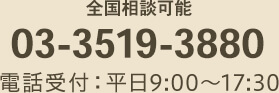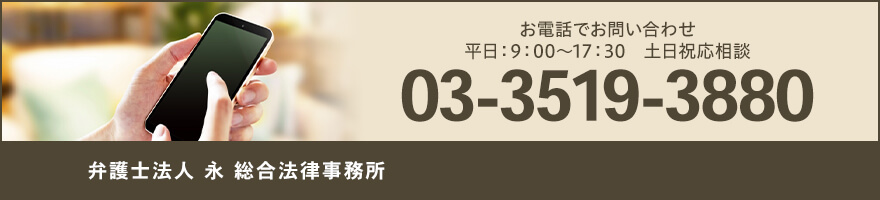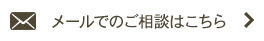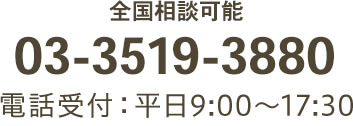Q 弊寺のお檀家が亡くなった後に、相続人を名乗る親族から「遺骨を引き渡してほしい」と要求されました。しかし、その一方で、別の親族からは「遺骨を絶対に渡すな」と逆の要望をされており、どうしたものかと困っております。お寺としてはどのように対応すべきでしょうか。
1 遺骨の法的性質と取り扱いの原則
檀信徒が亡くなった際にその相続人である親族間で争いがある場合に、遺骨の取扱いを含む祭祀承継に関して寺院が板挟みになってしまうことがあります。こうした場面において寺院が誤った対応をとってしまうと、後に相続人や利害関係人から損害賠償請求や訴訟などを起こされトラブルに発展してしまうリスクもあるため、法律に基づいた慎重かつ正しい対応が不可欠です。
法律上、お墓に関する権利については相続財産とは別途の財産として、その承継方法が定められています。
民法第896条では遺産の相続方法が定められていますが、その次条である第897条1項には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と規定され、続く第2項には「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」とされています。
ここにいう「系譜」とは家系図を、「祭具」とは仏壇仏具、位牌を、「墳墓」とは墓地及びその使用権を指しており、これらをまとめて「祭祀財産」と言います。祭祀財産は「祖先の祭祀を主宰すべき者」、つまり「祭祀主宰者」にすべて承継されることになりますが、上述のとおり祭祀財産の承継は相続法の適用外ですので、祭祀主宰者となる者は必ずしも相続人に限られないということになります。
なお、遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属するとされています(最高裁平成元年7月18日判決)。
2 祭祀主宰者の指定方法
祭祀主宰者については、上述のとおり「被相続人の指定」、「慣習」、または「家庭裁判所の指定」により定められます。
(1) 被相続人の指定
被相続人が祭祀主宰者を指定している場合は、その者が祭祀主宰者として祭祀財産を承継することになります(民法第897条1項但書)。
祭祀主宰者の指定方法や時期については特段の制限はありませんが、一般的には遺言書や生前の指定においてなされるのが通常です。これは文書による指定に限らず、口頭による指定であっても有効です。
(2) 慣習
被相続人が遺言書などにおいて生前に祭祀主宰者を指定していなかった場合には、慣習によって認められた祭祀主宰者が祭祀財産を承継することになります。
慣習とはその地方で一般に通用する習慣、しきたりのことをいいます。
戦前においては多くの場合に長男が祭祀主宰者となり祭祀承継することが慣習として認められていましたが、戦後に家の財産や地位を長男が相続するという家督制度が廃止されて以降、単に長男であるという事実だけで当然に祭祀主宰者になるという慣習は認められないことになっています。
(3) 家庭裁判所の指定
被相続人が祭祀主宰者を指定せず、なおかつ慣習上も誰を祭祀主宰者とすべきかが明らかではないという場合には、家庭裁判所が審判によって祭祀主宰者を指定することになります。
祭祀主宰者の指定に関する判断基準を明確に示した最高裁判例は現時点では見当たりません。
ただ、これについては東京高裁平成18年4月19日判決が「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」と判示し、詳細な判断基準を示している点が大変参考になります。
3 本ケースにおける対応
以上のとおり、遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属することになりますので、誰が祭祀主宰者なのかをきちんと確認することがお寺としては非常に重要です。この確認を怠って祭祀主宰者ではない別の親族に遺骨を渡してしまった場合、後日に真の祭祀主宰者から損害賠償や遺骨返還請求を受けるリスクがありますので十分に注意してください。
お寺としては、誰が正式な祭祀主宰者なのかを確認し、仮に親族間においてそれがまだ定まっていないということであれば遺骨の引き渡しをいったん留保し、遺言書や慣習、家庭裁判所の審判等により祭祀主宰者が定まるまでは寺院の納骨堂等において安全に管理しておくことになります。
亡くなられた檀信徒の親族とはいえ、不用意に遺骨を渡すことはお寺が親族間の相続トラブルに巻き込まれる危険性がありますので、慎重に対応することが肝要です。
檀信徒の遺族からの遺骨引渡し要求や祭祀主宰者の特定にかかるトラブルやお悩みの具体的な解決については、弁護士法人 永 総合法律事務所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
以 上